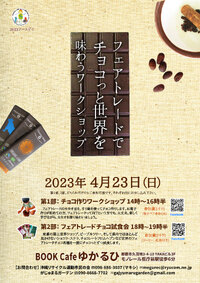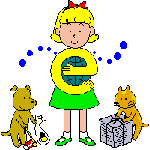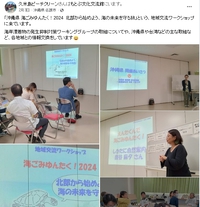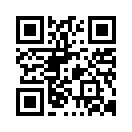2020年11月11日
フェアトレードに関する質問、その2
前回フェアトレードに関する質問の続きです。けっしてヒマではないんですが、長くなってしまいました。
■ フェアトレードラベルの問題点は?
認証ラベルの登場によって、フェアトレードの市場規模や、参加企業や生産者、そして製品を手にする消費者が飛躍的に広がったのは確かな事実です。ただ、そこにはどうしてもいろいろな問題がでてきます。英語版Wikipediaにもたくさんの議論がありますが、そのいくつかを挙げてみます。
■ フェアトレードラベルの問題点は?
認証ラベルの登場によって、フェアトレードの市場規模や、参加企業や生産者、そして製品を手にする消費者が飛躍的に広がったのは確かな事実です。ただ、そこにはどうしてもいろいろな問題がでてきます。英語版Wikipediaにもたくさんの議論がありますが、そのいくつかを挙げてみます。
【仕組みそのものの問題】

FI(Fairtrade International)ラベル認証のしくみ ※Fairtrade International https://www.fairtrade.net/より翻訳
フェアトレード・インターナショナルやレインフォレスト・アライアンスなどの認証ラベルは、生産者と販売業者の間に認証機関が入り、フェアトレードであることを確認し、証明します。これは先に述べた提携型フェアトレードが「直接的」であることと対照的に、「間接的」なシステムだと言えます。第三者だからこそ、公平にできるわけです。
認証する際、製造元やスーパー、コンビニなど販売する側が認証費用を払うのはもちろんですが、途上国の生産者も認証費や年会費を払って認証してもらうわけです。FI(Fairtrade International)の場合、その費用は、組合等の規模にもよりますが、年間約20万円かかるとのこと。(支援制度もあるそうですが)
弱い立場であるはずの生産者を守ることが目的なのに、その生産者からも認証料を取るという仕組みは、私はちょっとひっかかりました。お金がなければ参加できないのはおかしいですよね。
認証経費を上回る収入が保証されるならまだいいですが、認証事業者は「認証するだけ」で、実際に買い取る訳ではありません。最低価格は保証していますが、買い取り保証はありません。そもそも買い手が現れなければ、結局アンフェアなバイヤーに市場価格で売るしかありません。
その点について、(株)ヒロ・コーヒーの山本光弘さんが完結に説明していましたので、ちょっと長いけど引用します。
「提携型と認証型のフェアトレードの最大の違いは、「生産者にお金を支払うか、彼らからお金をもらうか」の違いだ。提携型の方では、自分たちが支援する農民なり、作業所なりといったところから、直接商品を買い取る。反面、認証型では、生産者(農園や組合)からお金をとって、フェアトレードの認証を行う。商品の買い取りはしないし、買い取り量(数)の保証もしない。買い取りは、彼らが「バイヤー」と呼んでいる業者 が行い、バイヤーがフェアトレード価格で生産者から商品を買い取る。(中略) フェアトレード認証組織は商品の買い取りにも販売にも、全く関わっていない」 https://www.hirocoffee.co.jp/hiro/farmkikou01.html
【完全な認証の困難さ】
フェアトレードラベルの利益が生産者の元にちゃんと届いているかについて、調査を元にした批判があります。現在FIでは、生産組合など組織化された生産者を対象としていますが、その全ての団体が実際に個々の農家に利益をきちんと分配しているかどうかを確かめるのは、現実的に非常に困難です。
FI認証農園を現地取材し、「アンフェア」な実態を告発する報道の中でも、『フェアトレードのおかしな真実』を読んだ多くの人が、「フェアトレードは偽善だ」と思うに違いありません。

『フェアトレードのおかしな真実』コナー・ウッドマン 英治出版 2013
もちろん全ての認証農園で不正が行われているわけではないでしょう。また、これらの批判は主に「認証システムが機能していない例がある」事実を指摘していますが、フェアトレードの仕組み自体が全く無意味とは主張していません。副題に「僕は本当に良いビジネスを探す旅に出た」とあるように、本の後半でエシカル・アディクションズやRare Tea Companyなどの、主にコーヒーロースター(焙煎業者)によるダイレクトトレードの取り組みが紹介されています。「認証組織を介さず直接生産者とやりとりしよう」とする姿勢は、「提携型フェアトレード」への原点回帰のようにも見えます。こちらやこちら
【エシカルウォッシュの問題】
フェアトレード・インターナショナルに限らず、他の認証システムや企業・業界の自己認証でも同じ問題があります。ごく一部の商品で得た認証を全体のように見せる、1%のフェアトレード商品を過大に宣伝し、99%のアンフェアを誤魔化そうとする企業がどうしても出てきます。これまでも環境分野でのグリーンウォッシュ、最近はSDGsウォッシュなど、いわゆる免罪符に利用されているという批判です。
フェアトレード・リソースセンター代表の北澤肯さんの報告。
「しかし、2005年に筆者がメキシコのコーヒー生産者組合UCIRI(フェアトレードラベルを、フランツ神父、ニコ氏とともに立ち上げた組合)を訪問し、フランツ神父にインタビューしたところ、神父は、『フェアトレードラベルは、スターバックスが使うラベルではなく、スターバックスに対抗するブランドであるべきだった』と言っていた。その後の展開を見て、ファトレードラベルは大きく道を間違えたと創始者の一人は悔いているのだ」
フェアトレードラベルの功罪を考える (北澤肯『アジ研ワールド・トレンド特集フェアトレードと貧困削減』2009)
ラベル認証について考える上で、とても示唆に飛んだ報告なのでぜひ上記リンクから全文を読んでほしいです。フェアトレードラベルはまだ「大いなる実験」であり、これからも世界の人々が育てていかなければならないものだと思います。
その他の批判としては、
「フェアトレード認証を受けた農家と受けていない農家に格差が生まれる」
「そもそも世界全体の市場に比べると、まだまだ規模が小さすぎる」
「市場価格は上がっているから、最低買取価格の意味がない」
というものもあります。(※最低価格は見直されることもあります)
私個人としては現在のFIフェアトレードラベルを始め、フェアトレードの信頼性を第三者が担保するしくみは必要だと思いますが、さらなる検証や批判はこれからも必要です。批判を通して、ダイレクトトレードの良さを取り入れるなど、さらに「フェア」な方法を探るしかありません。
■ なぜ日本の団体はラベル認証を取らないの?
日本のフェアトレード団体は、ピープルツリー(フェアトレードカンパニー)などわずかな例外を除けば、ラベル認証に消極的かまたは批判的に見えます。その理由としては、まず歴史的に、ラベル認証の誕生から統一の流れまでヨーロッパ主導で進んだということもあると思います。また、前述のラベル認証の抱えるいくつかの問題があるでしょう。
しかし、一般に同じ「フェアトレード」と呼ばれる事業をしている(ように見える)にも関わらず、手法や理念が明確に相反する部分が大きいことが、認証型フェアトレードに参加しない理由だと思います
【第三世界ショップ(プレス・オールターナティブ)】

第三世界ショップ フェアトレードは誰のためにあるの?
例えば、国内老舗団体の1つ、第三世界ショップ(プレス・オールターナティブ)はフェアトレードではなく「コミュニティトレード」という言葉を使っています。
「認証マークや基準の統一は消費者にとって分かりやすいというメリットがあります。しかし、フェアトレードの認証マークは、ついていれば安全とはしないで、「フェアトレードマークの意味」、「フェアトレードマークの背景」を、『考えたり』、『感じたり』するきっかけにして、自分で判断して、自分で感じていくことが大事だと考えています」
https://www.p-alt.co.jp/asante/pg402.html
【オルター・トレード・ジャパン】

季刊『at』3号2006年 オルター・トレード・ジャパンat編集室
フィリピンのネグロス危機で立ち上がったNGOが出発点のオルター・トレード・ジャパン(ATJ)は「民衆交易」と謳っています。その設立者である堀田正彦氏の批判は、さすが痛烈というか痛快です。
「問題は<フェアトレードマーク>というアイディアに潜んでいた「トロイの木馬」なのである。フェアトレード運動は、社会的なオルタナティヴ運動として、第一義的に、弱者の社会的権利を護り、拡大し、定着させようとする運動であり、これからもそうである。けっして、大企業を改心させてフェアな価格を生産者に払わせようという運動ではない。フェアトレードの中心にいる人々はその様に考えているはずである。しかし、メインストリームのスーパーマーケット市場にコーヒーという商品を売り出しはじめた時に取ったマーケティング戦略でしかなかった<フェアトレードマーク>が状況を複雑にしてしまった。
マークを認定するには「公正な第三者」という抽象的な存在が必要になる。かつ、「民主的である」ことを標榜するために、「認証基準」というものを公開し、その基準を満たせば「誰でもがフェアになれる」というシステムを作ってしまった。(中略)<フェアトレードマーク>は、その認証基準に以下のような一項をくけ加えておくべきだったのである。つまり「マークを使う企業は、その製品の51%以上がフェアトレード間商品でなければならない」という一項である」
前述の「エシカルウォッシュ」の説明の中で、北澤氏が引用したフランス神父(マックスハーベラーやFIの共同設立者)の言葉と趣旨は同じですね。せめてその企業の全製品のフェアトレード率をチェックしたいですよね〜。
【フェアトレードラベル離れが進むか?】
前回、FI以外の認証団体を紹介しましたが、認証ラベルの乱立、企業独自の認証の増加は、「FI離れ」ともいえる流れです。フェアトレードラベルの大口参加組織だった、イギリスの大手スーパーチェーン、セインズベリーSainsbury’sが、FIを辞め独自の"Farily Traded"に変えたという話。彼らの主張では、フェアトレードプレミアムの運用が不透明だというのが理由だと言っていますが、ようするに扱いが増えるほどFIに支払うライセンス料が莫大になったことが原因のようです。(参考1、参考2、参考3)
もちろんFIが万能ではないことをイギリスの消費者も知っているでしょうが、そう簡単にSainsbury’sにとって「コストが減ってラッキー!」とはならないと思います。他の国々も今後の動きを気にしておく必要がありますね。
■ なぜ日本ではフェアトレードが広がらないのか?
【日本で広がってない訳ではない】
まず世界の状況から。
FIは2018年、世界の2400社、また75カ国1240の生産者団体(166万戸)が参加。市場規模は98億ユーロ(1兆2千億円)。2008年の355億から10年で33倍に伸びています。また、イギリスではラベルの認知度93%とも言われます。

https://www.fairtrade.net/impact/overview
では国内はどうか。
まず認証ラベルの国内市場は、フェアトレードジャパンの報告によれば、国内でも認証ラベルによる市場は2019年で推定128億円。2009年の14億から10年間で8.8倍伸びています。つまり、日本でも広がってはいるが、欧米の急速な普及には追いついていない状況です。ただし気になる点は、2011年は年30%近く伸びたものの、ここ数年は成長率がは落ちており、2019年はついに前年比0.2%減とごくわずかながら減っている。
フェアトレードジャパン事業報告書・決算報告書 https://www.fairtrade-jp.org/about_us/accounting.php
2017年の各国のフェアトレード認証商品の市場規模と国民一人あたりの売上高をグラフにしてみました。日本は一人あたり年に95円にとどまっていますが、これでもかなり増えましたね。2009年は11.5円とかでした、、、

Fairtrade International-Report2017-18、世界の人口はこちらから
ただし、これはFI認証だけの売上です。では従来の提携型フェアトレードを含めた国内全体の市場はどうなっているでしょうか?
【認証型、提携型を含めた国内の市場規模】
提携型にも多くの団体があり、全国には小規模ながら多くのフェアトレードショップがあります。推計になりますが、一般財団法人国際貿易投資研究所ITIの2017年の市場調査では、2007年に73億円。2015年は265億円。8年で約3.6倍に増加しているそうです。(当会は完全に取り残されてました、、、)このうち、認証ラベル(FIとWFTO)が占める割合は、2015年の合計で44%を占めており、増加した分のうち認証ラベルの貢献度が非常に大きいことが分かります。認証ラベルの占める割合は、その後も増えているように感じます。
日本のフェアトレード市場調査2015 http://www.iti.or.jp/fairtrade2017.pdf
【なぜ広がりが遅いのか】
これはかなり私の憶測ですが、、、もともとフェアトレード運動の担い手にはキリスト教系のNGOなどが多く、キリスト教的な倫理観と組織的な取り組みによって広がっています。その背景には、かつての植民地支配に対する反省や、第二次大戦後のラテンアメリカやアフリカ諸国の債務危機に対する危機感が欧米諸国にあったのだと思います。(日本もアジア各地を植民地支配してましたけどね)
もちろん以前から日本にも、寄付型、慈善型の支援がありました。また欧米でも、かつての慈善的フェアトレードは伸び悩んでいたそうです。ということは、近年のフェアトレードの広がりの違いは、「認証型フェアトレードの普及度」の違いだと考えられます。認証型フェアトレードは前述したようにオランダなどで始まり、ここ10年から20年で欧米を中心に広がりました。ではなぜ日本では認証ラベルの普及が遅いのでしょうか。
日本にフェアトレードラベルを導入した松木傑氏は、今後、行政がバックアップするようになり、広がりだすはずと述べています。
「フェアトレードがグローバルな課題解決につながっているという認識を持てば、行政がそういうところをもう少しバックアップするのは自然であるし、おそらく、そうなっていくのではないだろうか。つまり世界の課題であるかぎり、フェアトレードがなくなることはないのです。日本でなかなかうまく普及しないというイライラは今もあるけれど、でも世界の課題があるかぎり、フェアトレードは広がっていくのが必然です。だから焦る必要はないとも思っています」(こちら)
たしかに行政の姿勢の差は大きいでしょう。世界にはまだフェアトレードを法律として定めた国はないようですが(※ブラジルやエクアドルなどは社会的連帯経済政策の中にフェアトレードを位置づけているようです)、欧州議会や欧州委員会は積極的に進めて行こうとしています。イギリスの場合は、ブレア元首相(在任1997-2007)が「エシカル」という言葉も広めたそうですし、英王室、特にチャールズ皇太子もはファトレードやエシカルに積極的だそうです。ロンドンオリンピックでも、フェアトレードが大きなテーマになりました(こちら)
フェアトレード推進の背景にある、CSR(企業の社会的責任)に関する制度や文化の違いも大きいでしょう。特ににラベル認証型フェアトレードの場合は、企業の参加が大きな目的ですので、企業側の姿勢が重要です。日本企業のCSRは環境に関する分野では進んでいますが、原料調達先(サプライヤー)の人権や労働についてはほぼ触れていないのが現状です。(企業のエシカル通信簿) 株主や消費者の関心が薄いということですね。
その他、論文をいくつか見ていたら、『フェアトレード運動の自由主義的転換』というのを見つけました。フェアトレード認証ラベルの誕生を「メインストリーム化」という概念で説明しており、当時のイギリスの政策との関連など、とても勉強になりました。
■ なぜ日本のフェアトレード商品は高いのか?
確かに日本ではフェアトレードというと「高い」というイメージがあります。一方ヨーロッパでは、フェアトレード商品は普通にスーパーに並んでおり、値段も一般の商品と比べてそれほど高くないと言われます。(※正確な比較調査は見つかりませんでした。どなたかご教示お願いします)
そもそもフェアトレードは、市場価格より高く買い取り、プレミアムと呼ばれる奨励金も払うため仕入れは一般市場価格より高くなるはず。ですが、実際のカフェのコーヒー1杯の値段の内分けは、ショップの家賃や人件費などの経費が多くを占めます。貨幣価値の違いもあるので、製造原価から考えるとコーヒー豆の仕入れ値というのは小売価格のうちせいぜい数円ほどだと考えられます。板チョコ(チョコレートバー)の場合も、カカオの原価は数パーセントと言われます。原料の仕入れ値が小売価格に与える影響はずっと小さいはずです。

映画『おいしいコーヒーの真実』公式サイトより https://www.uplink.co.jp/oishiicoffee/about_04.php
【国内の商品を比較】
国内のフェアトレードチョコを比較してみました。
当会が仕入れている第三世界ショップのフェアトレードチョコレートは100g程度の板チョコで648円くらいから。ピープルツリーは50gで378円。オルタートレードジャパンのインドネシア・パプア州現地製造のチョコは45gで832円!。イオンとなると85g、268円。カルディは50gで185円、(すべて税込み価格)。
・第三世界ショップ https://item.rakuten.co.jp/asante/10000424/ 認証なし
・ピープルツリー https://www.peopletree.co.jp/shopping/foods/078502.html WFTO認証
・ATJ https://www.aplashop.jp/SHOP/cco_ppc_milkcoco.html 認証なし
・イオントップバリュ https://www.topvalu.net/items/detail/4549741449793 FI認証
・カルディ https://www.kaldi.co.jp/ec/pro/disp/1/4515996911514 FI認証
※それぞれのフェアトレードミルクチョコ(イオンはダークのみでした)
いわゆるフェアトレードを専門に行っている上記3団体は高いですが、カルディやイオンなど一般の小売チェーン店で扱っている商品は、一般のチョコと比べてもやや高い程度、1.5〜2倍程度という感じです。
ただし、これらはカルディを除き、みな「輸入チョコ」だという点に注意が必要です。国産に比べ、輸送、関税などの費用がかかります。またフェアトレードと同時に「有機認証」も取っているなど、一般のチョコに比べて原材料にこだわっているため、どうしても高くなる傾向があると思います。また「乳化剤(大豆レシチン)を使わず伝統製法で72時間コンチングしました」など、製法でも差別化されていますね。でも、これは日本国内だけ高い理由にはなりません。
※なおイオンには粒チョコですが国内製造のフェアトレードチョコがありました。184g入で257円と、一般の商品を変わらない価格。でもよくみるとカカオ分が少ない「準チョコレート」ですね。(おいしさとは別ですよ)
これらの点をまとめて、高いと言われる理由を考えてみました。
【日本のフェアトレード商品が高い理由】
・国内で製造していない(海外から輸入している)ため
・市場規模が小さいのでスケールメリットがでない(もっとスーパーやコンビニで扱えば安くなる)
・原材料や製造、デザインなどで差別化するため
他にも、
・日本では一般の商品が低価格かつ品質が高いため、差別化が必要になる
・歴史的に関心が薄いからあまり売れず、高くなる
などの意見もあるようです。もっと市場規模が広がれば価格も安くなりそうです。
■ フェアトレードを広げるためには何が必要か?
最後の質問。(こんな難しいこと俺に聞くか?と思いました)
「現在のフェアトレードは民間のNGOや企業、市民が努力しているだけだから、どうしても限界がある。各国政府が法的な拘束力のある取り組みをする必要があるんじゃないか」と答えました。もう一つ、かつてアメリカに「ハーキン・エンゲル議定書」というものがあった(今もあるが)ことも話しました。

トム・ハーキン元米上院議員 "Chocolate's Child Slaves"(CNN)より
2001年、カカオ農園の奴隷労働の実態を伝える報道が相次いだことを受け、米上院議員のトム・ハーキンと下院議員エリオット・エンゲルが、カカオ製品に「奴隷不使用(スレイブフリー)マーク」をつける法案を出しました。しかしチョコレートメーカー各社が猛反発し、結局、法的強制力のない業界の努力目標のような「議定書」が結ばれ、2005年までに『最悪の形態の児童労働』をなくすことになりました。 『チョコレートの真実』(キャロル・オフ 英知出版)に詳しいです
しかしその後、取り組みは進まず、2008まで延長となりましたがそれでも実現できず、2021年までに再々延長という状況。今年来年が期限の年なんですね。さて現状はどうかというと、、、ちょっとショックな報道が今月ありました。

「現在も150万人の子どもがカカオ産業で労働させられており、2010年以降、30%増加している」
WashingtonPost シカゴ大学NORCの発表
「The country-specific data indicate that, in agricultural households in cocoa growing areas, 38 percent of children in Côte d’Ivoire and 55 percent of children in Ghana were engaged in child labor in cocoa production. Also, the country-specific data show that 37 percent of children in Côte d’Ivoire and 51 percent of children in Ghana were engaged in hazardous child labor in cocoa production. 」
(国別データでは、カカオ栽培地域の農業世帯において、コートジボワールでは38%、ガーナでは55%の子どもがカカオ生産で児童労働に従事していた。また、コートジボワールでは37%、ガーナでは51%の子どもたちが、カカオ生産において危険な児童労働に従事していたことがわかった)
その他、報道、団体も声明を出しています。ACE.org TheGuardian Swissinfo Confectionary News FIの声明
ここ数年、児童労働は減ってきているという話があったので、私もそう話していたのですが、この報道はかなり残念ですね。これは、現在のフェアトレードや国際組織、先進各国、多国籍企業の取り組みの限界を示しているのでしょうか。ハーキン・エンゲル議定書は、再々々延長してる場合じゃないです。
※NORC調査結果に対する世界カカオ財団の声明と、国際カカオイニシアチブの声明

FI(Fairtrade International)ラベル認証のしくみ ※Fairtrade International https://www.fairtrade.net/より翻訳
フェアトレード・インターナショナルやレインフォレスト・アライアンスなどの認証ラベルは、生産者と販売業者の間に認証機関が入り、フェアトレードであることを確認し、証明します。これは先に述べた提携型フェアトレードが「直接的」であることと対照的に、「間接的」なシステムだと言えます。第三者だからこそ、公平にできるわけです。
認証する際、製造元やスーパー、コンビニなど販売する側が認証費用を払うのはもちろんですが、途上国の生産者も認証費や年会費を払って認証してもらうわけです。FI(Fairtrade International)の場合、その費用は、組合等の規模にもよりますが、年間約20万円かかるとのこと。(支援制度もあるそうですが)
弱い立場であるはずの生産者を守ることが目的なのに、その生産者からも認証料を取るという仕組みは、私はちょっとひっかかりました。お金がなければ参加できないのはおかしいですよね。
認証経費を上回る収入が保証されるならまだいいですが、認証事業者は「認証するだけ」で、実際に買い取る訳ではありません。最低価格は保証していますが、買い取り保証はありません。そもそも買い手が現れなければ、結局アンフェアなバイヤーに市場価格で売るしかありません。
その点について、(株)ヒロ・コーヒーの山本光弘さんが完結に説明していましたので、ちょっと長いけど引用します。
「提携型と認証型のフェアトレードの最大の違いは、「生産者にお金を支払うか、彼らからお金をもらうか」の違いだ。提携型の方では、自分たちが支援する農民なり、作業所なりといったところから、直接商品を買い取る。反面、認証型では、生産者(農園や組合)からお金をとって、フェアトレードの認証を行う。商品の買い取りはしないし、買い取り量(数)の保証もしない。買い取りは、彼らが「バイヤー」と呼んでいる業者 が行い、バイヤーがフェアトレード価格で生産者から商品を買い取る。(中略) フェアトレード認証組織は商品の買い取りにも販売にも、全く関わっていない」 https://www.hirocoffee.co.jp/hiro/farmkikou01.html
【完全な認証の困難さ】
フェアトレードラベルの利益が生産者の元にちゃんと届いているかについて、調査を元にした批判があります。現在FIでは、生産組合など組織化された生産者を対象としていますが、その全ての団体が実際に個々の農家に利益をきちんと分配しているかどうかを確かめるのは、現実的に非常に困難です。
FI認証農園を現地取材し、「アンフェア」な実態を告発する報道の中でも、『フェアトレードのおかしな真実』を読んだ多くの人が、「フェアトレードは偽善だ」と思うに違いありません。

『フェアトレードのおかしな真実』コナー・ウッドマン 英治出版 2013
もちろん全ての認証農園で不正が行われているわけではないでしょう。また、これらの批判は主に「認証システムが機能していない例がある」事実を指摘していますが、フェアトレードの仕組み自体が全く無意味とは主張していません。副題に「僕は本当に良いビジネスを探す旅に出た」とあるように、本の後半でエシカル・アディクションズやRare Tea Companyなどの、主にコーヒーロースター(焙煎業者)によるダイレクトトレードの取り組みが紹介されています。「認証組織を介さず直接生産者とやりとりしよう」とする姿勢は、「提携型フェアトレード」への原点回帰のようにも見えます。こちらやこちら
【エシカルウォッシュの問題】
フェアトレード・インターナショナルに限らず、他の認証システムや企業・業界の自己認証でも同じ問題があります。ごく一部の商品で得た認証を全体のように見せる、1%のフェアトレード商品を過大に宣伝し、99%のアンフェアを誤魔化そうとする企業がどうしても出てきます。これまでも環境分野でのグリーンウォッシュ、最近はSDGsウォッシュなど、いわゆる免罪符に利用されているという批判です。
フェアトレード・リソースセンター代表の北澤肯さんの報告。
「しかし、2005年に筆者がメキシコのコーヒー生産者組合UCIRI(フェアトレードラベルを、フランツ神父、ニコ氏とともに立ち上げた組合)を訪問し、フランツ神父にインタビューしたところ、神父は、『フェアトレードラベルは、スターバックスが使うラベルではなく、スターバックスに対抗するブランドであるべきだった』と言っていた。その後の展開を見て、ファトレードラベルは大きく道を間違えたと創始者の一人は悔いているのだ」
フェアトレードラベルの功罪を考える (北澤肯『アジ研ワールド・トレンド特集フェアトレードと貧困削減』2009)
ラベル認証について考える上で、とても示唆に飛んだ報告なのでぜひ上記リンクから全文を読んでほしいです。フェアトレードラベルはまだ「大いなる実験」であり、これからも世界の人々が育てていかなければならないものだと思います。
その他の批判としては、
「フェアトレード認証を受けた農家と受けていない農家に格差が生まれる」
「そもそも世界全体の市場に比べると、まだまだ規模が小さすぎる」
「市場価格は上がっているから、最低買取価格の意味がない」
というものもあります。(※最低価格は見直されることもあります)
私個人としては現在のFIフェアトレードラベルを始め、フェアトレードの信頼性を第三者が担保するしくみは必要だと思いますが、さらなる検証や批判はこれからも必要です。批判を通して、ダイレクトトレードの良さを取り入れるなど、さらに「フェア」な方法を探るしかありません。
■ なぜ日本の団体はラベル認証を取らないの?
日本のフェアトレード団体は、ピープルツリー(フェアトレードカンパニー)などわずかな例外を除けば、ラベル認証に消極的かまたは批判的に見えます。その理由としては、まず歴史的に、ラベル認証の誕生から統一の流れまでヨーロッパ主導で進んだということもあると思います。また、前述のラベル認証の抱えるいくつかの問題があるでしょう。
しかし、一般に同じ「フェアトレード」と呼ばれる事業をしている(ように見える)にも関わらず、手法や理念が明確に相反する部分が大きいことが、認証型フェアトレードに参加しない理由だと思います
【第三世界ショップ(プレス・オールターナティブ)】

第三世界ショップ フェアトレードは誰のためにあるの?
例えば、国内老舗団体の1つ、第三世界ショップ(プレス・オールターナティブ)はフェアトレードではなく「コミュニティトレード」という言葉を使っています。
「認証マークや基準の統一は消費者にとって分かりやすいというメリットがあります。しかし、フェアトレードの認証マークは、ついていれば安全とはしないで、「フェアトレードマークの意味」、「フェアトレードマークの背景」を、『考えたり』、『感じたり』するきっかけにして、自分で判断して、自分で感じていくことが大事だと考えています」
https://www.p-alt.co.jp/asante/pg402.html
【オルター・トレード・ジャパン】

季刊『at』3号2006年 オルター・トレード・ジャパンat編集室
フィリピンのネグロス危機で立ち上がったNGOが出発点のオルター・トレード・ジャパン(ATJ)は「民衆交易」と謳っています。その設立者である堀田正彦氏の批判は、さすが痛烈というか痛快です。
「問題は<フェアトレードマーク>というアイディアに潜んでいた「トロイの木馬」なのである。フェアトレード運動は、社会的なオルタナティヴ運動として、第一義的に、弱者の社会的権利を護り、拡大し、定着させようとする運動であり、これからもそうである。けっして、大企業を改心させてフェアな価格を生産者に払わせようという運動ではない。フェアトレードの中心にいる人々はその様に考えているはずである。しかし、メインストリームのスーパーマーケット市場にコーヒーという商品を売り出しはじめた時に取ったマーケティング戦略でしかなかった<フェアトレードマーク>が状況を複雑にしてしまった。
マークを認定するには「公正な第三者」という抽象的な存在が必要になる。かつ、「民主的である」ことを標榜するために、「認証基準」というものを公開し、その基準を満たせば「誰でもがフェアになれる」というシステムを作ってしまった。(中略)<フェアトレードマーク>は、その認証基準に以下のような一項をくけ加えておくべきだったのである。つまり「マークを使う企業は、その製品の51%以上がフェアトレード間商品でなければならない」という一項である」
前述の「エシカルウォッシュ」の説明の中で、北澤氏が引用したフランス神父(マックスハーベラーやFIの共同設立者)の言葉と趣旨は同じですね。せめてその企業の全製品のフェアトレード率をチェックしたいですよね〜。
【フェアトレードラベル離れが進むか?】
前回、FI以外の認証団体を紹介しましたが、認証ラベルの乱立、企業独自の認証の増加は、「FI離れ」ともいえる流れです。フェアトレードラベルの大口参加組織だった、イギリスの大手スーパーチェーン、セインズベリーSainsbury’sが、FIを辞め独自の"Farily Traded"に変えたという話。彼らの主張では、フェアトレードプレミアムの運用が不透明だというのが理由だと言っていますが、ようするに扱いが増えるほどFIに支払うライセンス料が莫大になったことが原因のようです。(参考1、参考2、参考3)
もちろんFIが万能ではないことをイギリスの消費者も知っているでしょうが、そう簡単にSainsbury’sにとって「コストが減ってラッキー!」とはならないと思います。他の国々も今後の動きを気にしておく必要がありますね。
■ なぜ日本ではフェアトレードが広がらないのか?
【日本で広がってない訳ではない】
まず世界の状況から。
FIは2018年、世界の2400社、また75カ国1240の生産者団体(166万戸)が参加。市場規模は98億ユーロ(1兆2千億円)。2008年の355億から10年で33倍に伸びています。また、イギリスではラベルの認知度93%とも言われます。

https://www.fairtrade.net/impact/overview
では国内はどうか。
まず認証ラベルの国内市場は、フェアトレードジャパンの報告によれば、国内でも認証ラベルによる市場は2019年で推定128億円。2009年の14億から10年間で8.8倍伸びています。つまり、日本でも広がってはいるが、欧米の急速な普及には追いついていない状況です。ただし気になる点は、2011年は年30%近く伸びたものの、ここ数年は成長率がは落ちており、2019年はついに前年比0.2%減とごくわずかながら減っている。
フェアトレードジャパン事業報告書・決算報告書 https://www.fairtrade-jp.org/about_us/accounting.php
2017年の各国のフェアトレード認証商品の市場規模と国民一人あたりの売上高をグラフにしてみました。日本は一人あたり年に95円にとどまっていますが、これでもかなり増えましたね。2009年は11.5円とかでした、、、

Fairtrade International-Report2017-18、世界の人口はこちらから
ただし、これはFI認証だけの売上です。では従来の提携型フェアトレードを含めた国内全体の市場はどうなっているでしょうか?
【認証型、提携型を含めた国内の市場規模】
提携型にも多くの団体があり、全国には小規模ながら多くのフェアトレードショップがあります。推計になりますが、一般財団法人国際貿易投資研究所ITIの2017年の市場調査では、2007年に73億円。2015年は265億円。8年で約3.6倍に増加しているそうです。(当会は完全に取り残されてました、、、)このうち、認証ラベル(FIとWFTO)が占める割合は、2015年の合計で44%を占めており、増加した分のうち認証ラベルの貢献度が非常に大きいことが分かります。認証ラベルの占める割合は、その後も増えているように感じます。
日本のフェアトレード市場調査2015 http://www.iti.or.jp/fairtrade2017.pdf
【なぜ広がりが遅いのか】
これはかなり私の憶測ですが、、、もともとフェアトレード運動の担い手にはキリスト教系のNGOなどが多く、キリスト教的な倫理観と組織的な取り組みによって広がっています。その背景には、かつての植民地支配に対する反省や、第二次大戦後のラテンアメリカやアフリカ諸国の債務危機に対する危機感が欧米諸国にあったのだと思います。(日本もアジア各地を植民地支配してましたけどね)
もちろん以前から日本にも、寄付型、慈善型の支援がありました。また欧米でも、かつての慈善的フェアトレードは伸び悩んでいたそうです。ということは、近年のフェアトレードの広がりの違いは、「認証型フェアトレードの普及度」の違いだと考えられます。認証型フェアトレードは前述したようにオランダなどで始まり、ここ10年から20年で欧米を中心に広がりました。ではなぜ日本では認証ラベルの普及が遅いのでしょうか。
日本にフェアトレードラベルを導入した松木傑氏は、今後、行政がバックアップするようになり、広がりだすはずと述べています。
「フェアトレードがグローバルな課題解決につながっているという認識を持てば、行政がそういうところをもう少しバックアップするのは自然であるし、おそらく、そうなっていくのではないだろうか。つまり世界の課題であるかぎり、フェアトレードがなくなることはないのです。日本でなかなかうまく普及しないというイライラは今もあるけれど、でも世界の課題があるかぎり、フェアトレードは広がっていくのが必然です。だから焦る必要はないとも思っています」(こちら)
たしかに行政の姿勢の差は大きいでしょう。世界にはまだフェアトレードを法律として定めた国はないようですが(※ブラジルやエクアドルなどは社会的連帯経済政策の中にフェアトレードを位置づけているようです)、欧州議会や欧州委員会は積極的に進めて行こうとしています。イギリスの場合は、ブレア元首相(在任1997-2007)が「エシカル」という言葉も広めたそうですし、英王室、特にチャールズ皇太子もはファトレードやエシカルに積極的だそうです。ロンドンオリンピックでも、フェアトレードが大きなテーマになりました(こちら)
フェアトレード推進の背景にある、CSR(企業の社会的責任)に関する制度や文化の違いも大きいでしょう。特ににラベル認証型フェアトレードの場合は、企業の参加が大きな目的ですので、企業側の姿勢が重要です。日本企業のCSRは環境に関する分野では進んでいますが、原料調達先(サプライヤー)の人権や労働についてはほぼ触れていないのが現状です。(企業のエシカル通信簿) 株主や消費者の関心が薄いということですね。
その他、論文をいくつか見ていたら、『フェアトレード運動の自由主義的転換』というのを見つけました。フェアトレード認証ラベルの誕生を「メインストリーム化」という概念で説明しており、当時のイギリスの政策との関連など、とても勉強になりました。
■ なぜ日本のフェアトレード商品は高いのか?
確かに日本ではフェアトレードというと「高い」というイメージがあります。一方ヨーロッパでは、フェアトレード商品は普通にスーパーに並んでおり、値段も一般の商品と比べてそれほど高くないと言われます。(※正確な比較調査は見つかりませんでした。どなたかご教示お願いします)
そもそもフェアトレードは、市場価格より高く買い取り、プレミアムと呼ばれる奨励金も払うため仕入れは一般市場価格より高くなるはず。ですが、実際のカフェのコーヒー1杯の値段の内分けは、ショップの家賃や人件費などの経費が多くを占めます。貨幣価値の違いもあるので、製造原価から考えるとコーヒー豆の仕入れ値というのは小売価格のうちせいぜい数円ほどだと考えられます。板チョコ(チョコレートバー)の場合も、カカオの原価は数パーセントと言われます。原料の仕入れ値が小売価格に与える影響はずっと小さいはずです。

映画『おいしいコーヒーの真実』公式サイトより https://www.uplink.co.jp/oishiicoffee/about_04.php
【国内の商品を比較】
国内のフェアトレードチョコを比較してみました。
当会が仕入れている第三世界ショップのフェアトレードチョコレートは100g程度の板チョコで648円くらいから。ピープルツリーは50gで378円。オルタートレードジャパンのインドネシア・パプア州現地製造のチョコは45gで832円!。イオンとなると85g、268円。カルディは50gで185円、(すべて税込み価格)。
・第三世界ショップ https://item.rakuten.co.jp/asante/10000424/ 認証なし
・ピープルツリー https://www.peopletree.co.jp/shopping/foods/078502.html WFTO認証
・ATJ https://www.aplashop.jp/SHOP/cco_ppc_milkcoco.html 認証なし
・イオントップバリュ https://www.topvalu.net/items/detail/4549741449793 FI認証
・カルディ https://www.kaldi.co.jp/ec/pro/disp/1/4515996911514 FI認証
※それぞれのフェアトレードミルクチョコ(イオンはダークのみでした)
いわゆるフェアトレードを専門に行っている上記3団体は高いですが、カルディやイオンなど一般の小売チェーン店で扱っている商品は、一般のチョコと比べてもやや高い程度、1.5〜2倍程度という感じです。
ただし、これらはカルディを除き、みな「輸入チョコ」だという点に注意が必要です。国産に比べ、輸送、関税などの費用がかかります。またフェアトレードと同時に「有機認証」も取っているなど、一般のチョコに比べて原材料にこだわっているため、どうしても高くなる傾向があると思います。また「乳化剤(大豆レシチン)を使わず伝統製法で72時間コンチングしました」など、製法でも差別化されていますね。でも、これは日本国内だけ高い理由にはなりません。
※なおイオンには粒チョコですが国内製造のフェアトレードチョコがありました。184g入で257円と、一般の商品を変わらない価格。でもよくみるとカカオ分が少ない「準チョコレート」ですね。(おいしさとは別ですよ)
これらの点をまとめて、高いと言われる理由を考えてみました。
【日本のフェアトレード商品が高い理由】
・国内で製造していない(海外から輸入している)ため
・市場規模が小さいのでスケールメリットがでない(もっとスーパーやコンビニで扱えば安くなる)
・原材料や製造、デザインなどで差別化するため
他にも、
・日本では一般の商品が低価格かつ品質が高いため、差別化が必要になる
・歴史的に関心が薄いからあまり売れず、高くなる
などの意見もあるようです。もっと市場規模が広がれば価格も安くなりそうです。
■ フェアトレードを広げるためには何が必要か?
最後の質問。(こんな難しいこと俺に聞くか?と思いました)
「現在のフェアトレードは民間のNGOや企業、市民が努力しているだけだから、どうしても限界がある。各国政府が法的な拘束力のある取り組みをする必要があるんじゃないか」と答えました。もう一つ、かつてアメリカに「ハーキン・エンゲル議定書」というものがあった(今もあるが)ことも話しました。

トム・ハーキン元米上院議員 "Chocolate's Child Slaves"(CNN)より
2001年、カカオ農園の奴隷労働の実態を伝える報道が相次いだことを受け、米上院議員のトム・ハーキンと下院議員エリオット・エンゲルが、カカオ製品に「奴隷不使用(スレイブフリー)マーク」をつける法案を出しました。しかしチョコレートメーカー各社が猛反発し、結局、法的強制力のない業界の努力目標のような「議定書」が結ばれ、2005年までに『最悪の形態の児童労働』をなくすことになりました。 『チョコレートの真実』(キャロル・オフ 英知出版)に詳しいです
しかしその後、取り組みは進まず、2008まで延長となりましたがそれでも実現できず、2021年までに再々延長という状況。

「現在も150万人の子どもがカカオ産業で労働させられており、2010年以降、30%増加している」
WashingtonPost シカゴ大学NORCの発表
「The country-specific data indicate that, in agricultural households in cocoa growing areas, 38 percent of children in Côte d’Ivoire and 55 percent of children in Ghana were engaged in child labor in cocoa production. Also, the country-specific data show that 37 percent of children in Côte d’Ivoire and 51 percent of children in Ghana were engaged in hazardous child labor in cocoa production. 」
(国別データでは、カカオ栽培地域の農業世帯において、コートジボワールでは38%、ガーナでは55%の子どもがカカオ生産で児童労働に従事していた。また、コートジボワールでは37%、ガーナでは51%の子どもたちが、カカオ生産において危険な児童労働に従事していたことがわかった)
その他、報道、団体も声明を出しています。ACE.org TheGuardian Swissinfo Confectionary News FIの声明
ここ数年、児童労働は減ってきているという話があったので、私もそう話していたのですが、この報道はかなり残念ですね。これは、現在のフェアトレードや国際組織、先進各国、多国籍企業の取り組みの限界を示しているのでしょうか。ハーキン・エンゲル議定書は、再々々延長してる場合じゃないです。
※NORC調査結果に対する世界カカオ財団の声明と、国際カカオイニシアチブの声明
Posted by くるくるリサイクル at 18:06│Comments(0)
│エコ・フェアトレードショップ